地代を滞納されたらどうする?地主ができる交渉・通知・法的対応までの流れ
「今月まだ入金されてないな…」
そんなふうに思ったまま、1ヶ月、2ヶ月と滞納が続いてしまっている地代。
借地人との関係性を考えると、「請求するのも気が引ける」と悩む地主の方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、放置すればするほど、相手にとっても「何も言われないなら払わなくても大丈夫」といった誤解が生まれ、契約関係の信頼性が損なわれていくリスクがあります。
この記事では、地代の滞納が起きた際に、地主としてとれる具体的な対応の流れを、実務視点で丁寧に整理してお伝えします。
催促が初めての方でも安心して踏み出せるよう、「強く出す」前にできることから、「裁判も視野に入れる」までの現実的な選択肢を一緒に見ていきましょう。
この記事でわかること
・地代滞納が発生したときの初期対応と記録の残し方
・通知・催促・内容証明などの活用ポイント
・最終的に裁判を視野に入れる場合の流れと注意点
地代滞納が起きたとき、まず地主が知っておくべきこと
「1回だけの遅れ」でも無視しないほうがいい理由
地代の遅れは、「たまたま」「一時的な事情」ということもあるでしょう。
ですが、1回の遅れをそのまま放置してしまうと、相手に“払わなくても催促されない”という誤解を与えるリスクがあります。
それが2回、3回と続くうちに、「この地主は何も言ってこないから…」といった油断が生まれ、やがて契約関係自体が軽んじられることにもつながりかねません。
また、将来的に地代未払いを理由に契約解除や法的請求を行う場面では、最初の滞納にどう対応したかが重要視されます。
初期対応の原則は「記録を残す」「冷静に伝える」
まずは電話や直接の声かけなど、穏やかな確認からスタートしても構いません。
ただし、そのやり取りも後で証拠として残せるよう、メモや日付入りの記録を残しておくのが大切です。
「○月○日に確認した」「○○と言われた」「○月末までに支払うと言っていた」など、簡単でもいいので残しておくことで、のちの交渉や法的対応でも主張の根拠になります。
地主の言動がのちの交渉材料にもなる
地代滞納のような問題は、感情的になればなるほどこじれがちです。
だからこそ、地主側が「冷静に、段階を踏んで対応している」という証拠を残しておくことが、交渉力にもつながります。
「こちらはきちんと伝えた」「それでも支払われなかった」というプロセスがはっきりしていれば、内容証明や法的手段に進む場合も、相手の反論が通りにくくなります。
滞納が続く場合の通知・交渉・法的ステップ
内容証明は「最終手段」ではなく“冷静な意思表明”
借地人が期日を守らないまま滞納が続く場合、口頭でのやり取りだけでは限界があります。
そんなとき有効なのが、内容証明郵便による正式な催告です。
内容証明というと「いきなり強硬手段?」と感じるかもしれませんが、“法的に有効な通知”として記録を残す手段であり、冷静な意思表明でもあります。
たとえば:
- 「○月分の地代○○円が未納となっています」
- 「○月○日までにお支払いがない場合、契約に基づきしかるべき対応を検討いたします」
このように事実と期限を明記することで、相手にも「これは正式な手続きだ」と認識させることができます。
更新料や損害金は取れる?契約内容と交渉次第で対応可能
契約書の内容によっては、更新料や遅延損害金の請求が可能なケースもあります。
記載がなくても、法定利率(年3%)に基づく損害金請求を行うことは可能です。
また、金額が少額であっても「いつからの未納で、いくらになるのか」を整理しておくことで、交渉時の材料になります。
支払いが困難な事情がある場合は、「分割での支払い」「期限付き猶予」などの提案を地主側から行うのも一つの手です。
裁判を視野に入れるなら…少額訴訟や差押えの現実性も確認
内容証明を送っても支払いがない場合は、法的手段(裁判)による回収を検討することになります。
60万円以下の請求であれば、少額訴訟という簡易な制度を使うことも可能です。
これは地主自身が本人で申し立て可能で、原則1回の審理で判決が出るため、費用・期間の負担も小さいのが特徴です。
勝訴すれば預金や給与などの差押えも法的には可能ですが、実際に回収できるかどうかは、借地人の資力や情報の有無にも左右されます。
このように、裁判を見据える場合でも「最終的にどうなるか」を考えながら、穏やかな和解や再建の道も検討していくことが現実的です。
トラブルを繰り返さないための「予防」と「整え直し」
支払期日・方法・連絡手段を明文化しておく
滞納トラブルは、そもそも「何日までに、どう支払うか」が曖昧なままになっていることが原因の場合もあります。
特に口約束で続けてきた契約では、当事者同士の感覚のズレが大きなリスクになります。
今後のためにも、以下のような点は書面で確認・合意しておくのがおすすめです:
- 毎月の支払期日(○日まで)
- 支払い方法(振込先/現金手渡しなど)
- 滞納時の連絡・催告の方法
契約書が正式にない場合でも、「確認書」「覚書」といった簡単な形式でも十分です。
猶予するなら“期限と条件”を明示しておく
借地人が一時的に支払いが難しいという事情を抱えていた場合、配慮として猶予に応じるのも一つの対応です。
ただし、それを“なあなあ”にしてしまうと、「払わなくても許される」という誤解を招きます。
たとえば:
- 「○月末までは猶予するが、それまでにまとめて支払うこと」
- 「分割で○ヶ月以内に完済する」
このように具体的な期限・条件を文書に残すことで、トラブルの再発防止にもなりますし、将来的な証拠としても有効です。
早めに第三者に相談するのも選択肢
「自分ではうまく言えない」「交渉がストレスになる」――そんなときは、第三者のサポートを活用するのも有効です。
弁護士に限らず、行政書士や司法書士、一部自治体の無料相談窓口など、地主側が気軽に相談できる機関もあります。
“間に入ってもらう”ことで、感情的にならず冷静に進めやすくなり、借地人との信頼関係を保ったまま、整理や改善がしやすくなります。
まとめ|地代滞納への対応は“冷静な記録と行動”がカギ
借地人との関係性や長年の付き合いがあると、「強く言いづらい」「我慢してしまう」と感じてしまうもの。
ですが、地代の滞納はそのままにしておくと、関係性だけでなく契約そのものの信頼性も損なわれかねません。
この記事では、地代滞納が起きたときに地主ができるステップとして:
- 最初は冷静に事実確認し、記録を残すこと
- 催告は通知として行い、内容証明も視野に入れる
- どうしても支払いがなければ裁判や差押えも可能
- 再発防止には契約内容の明文化や第三者の関与も有効
といった具体策をご紹介しました。
大切なのは、怒りに任せるのではなく、相手のためにも“整理しておくこと”が双方の利益になるという視点です。
同じように悩む地主の方へ
「こんなこと誰に相談すればいいの?」
そう感じている方のために、無料で相談できる専門窓口もご案内しています。
まずは現状を一緒に整理してみませんか?
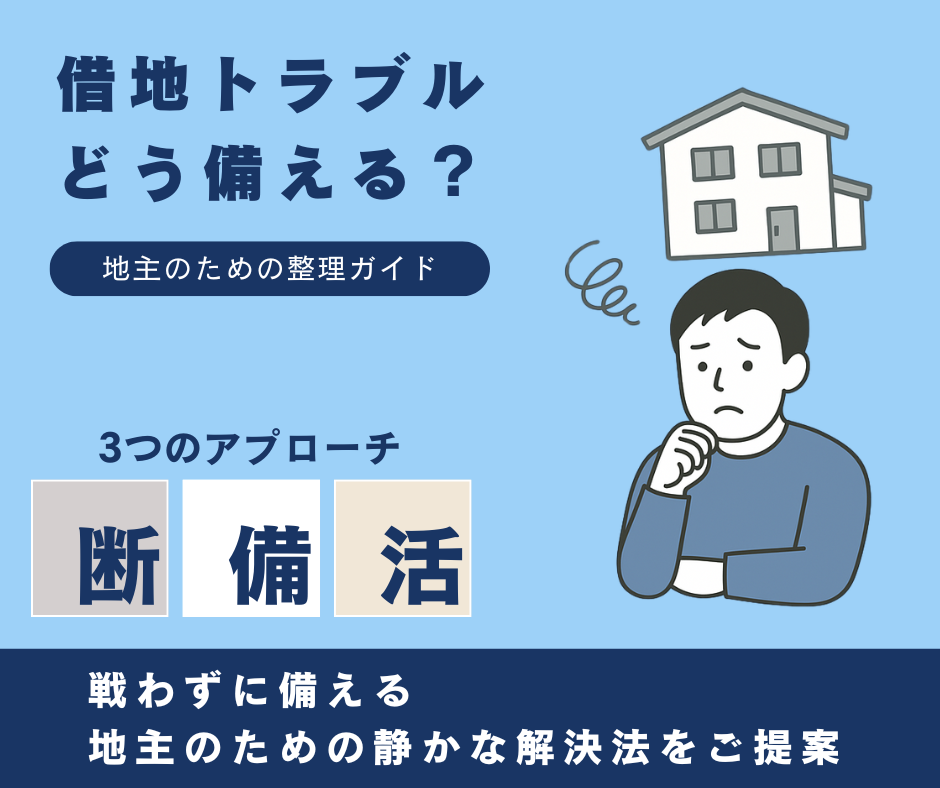
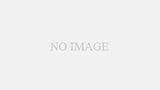
コメント