地代を滞納されたらどうする?「まずやるべきこと」と契約に備える3つの視点
「地代の振り込みがない…」「何度か催促したけど、また遅れてる」
そんな借地人とのトラブルは、珍しいことではありません。
感情的に動いてしまうと関係がこじれやすく、逆に遠慮しすぎるとズルズルと滞納が続いてしまうことも。
この記事では、借地人が地代を滞納したときに地主が冷静にとるべき対応と判断のステップを3つに分けて解説します。
感情と制度の間で悩んでいる方へ、契約と信頼を守るための実務的な道筋をご紹介します。
地代が滞納された…まず確認すべき3つの視点
借地人からの地代が滞っている──
そんなとき、最初にやるべきことは「感情で動くこと」ではなく、事実と契約の確認です。
たとえ長年の付き合いであっても、契約は契約。
対応を誤ると、回収不能やトラブルの長期化にもつながりかねません。
契約書の内容を確認する(支払期限・解除条件)
まず手元の借地契約書を確認しましょう。以下のような項目が、対応を判断する基準になります:
- 地代の支払期日と方法(口座振込・手渡しなど)
- 遅延に関する条項(何日までに/利息の有無)
- 契約解除の条件(◯ヶ月以上の滞納で解除可能 など)
「契約書が古くて書いていない」「曖昧なまま口約束で続いていた」場合は、更新時に見直す必要性も含めて検討対象になります。
滞納の期間と、借地人の対応姿勢を見る
「1週間遅れた」だけと、「2か月分未納」はまったく意味が違います。
また、借地人が「謝罪してすぐ支払う」のか、「言い訳を重ねて先延ばしにする」のかによって、対応の温度感も変わってきます。
まずは滞納の「期間」と「相手の反応」を冷静に整理しましょう。
感情より「記録と証拠」が先──今すぐできる備え
「言いにくい」「長年の付き合いだから…」という気持ちは自然なことです。
でも、万が一の法的手続きに備えるなら、口頭でのやりとりより、記録が残る通知が重要になります。
- 支払いの遅れを記録するメモ(いつ・どのくらい)
- LINEやメールでのやりとり
- 簡易的な通知文(普通郵便でもOK)
こうした記録が、後に「催促した事実」「期限を伝えた証拠」となり、次のアクションへの道を開きます。
次のステップでは、通知・催促・内容証明の違いや使い分け方について解説します。
催促・通知・内容証明の違いと使い分け
地代の滞納に気づいたとき、多くの地主がまず感じるのは「言い出しづらさ」です。
ですが、通知の仕方には段階と選択肢があり、「重くない伝え方」も十分可能です。
口頭での催促だけでは不十分な理由
「電話で言った」「会ったときに話した」──これだけでは、後で証拠として残りません。
トラブルが長期化した際、「こちらは催促した」ことを客観的に示す記録がなければ、契約解除や法的整理に進む際に不利になることもあります。
「内容証明」は強硬手段じゃない、“意思表示”の一つ
内容証明郵便というと、「裁判の前触れ」「喧嘩腰」といった印象を持たれがちですが、実際は「こういう状況ですよ」と丁寧に知らせるための正式な通知です。
文面も自由度があり、やさしいトーンで伝える内容証明も可能です。
たとえば:
「地代の件でご確認いただきたく、失礼ながら書面にてご案内差し上げます。ご都合が許せば、ご対応いただけますと幸いです。」
このような表現であれば、関係を壊さずに通知できる手段として活用できます。
選択肢は「催促する or 黙る」だけじゃない
催促というと、どうしても「相手にプレッシャーをかける」イメージになりがちですが、「状況を確認したい」レベルで伝えることも可能です。
通知は、自分を守ると同時に、相手に“考えるきっかけ”を与える手段でもあるのです。
次のステップでは、こうしたやりとりが「一度きり」で終わらないようにするために、契約更新や予防策として盛り込めるポイントを整理していきます。
再発させないために、契約更新時に備えておくこと
地代の滞納に対する対応が一段落しても、「また同じことが起きたら…」という不安は消えません。
そこで重要になるのが、契約を更新するタイミングでの見直しです。
「過去に困ったこと」があったからこそ、未来のための条項を盛り込むチャンスでもあります。
滞納時の解除条項を盛り込む
たとえば、以下のような条項を明記しておくことで、次回以降の対応がスムーズになります:
- ◯ヶ月以上滞納した場合は契約解除の申し出が可能
- 催告通知後◯日以内に支払いがなければ、契約見直しの対象とする
こうした条項があるだけで、「何もできない」という状態を避けることができます。
緊急連絡先・支払い猶予条件なども明文化を
高齢の借地人や単身世帯の場合、支払いが遅れた際の連絡先がわからず困ることもあります。
更新時には、「緊急連絡先の届出義務」や「支払いが遅れた場合の対応フロー」などを
事前に取り決めておくと、トラブルの芽を小さいうちに摘むことができます。
“情と制度”のバランスがとれる関係づくりを意識する
大切なのは、制度だけに頼るのではなく、日常的なコミュニケーションも合わせて整えることです。
「困っていることがあれば相談してほしい」
「お互いに気持ちよく契約を続けたい」
そんなスタンスを伝えておくことで、信頼関係をベースにした契約へと近づけることができます。
この記事が、対応に迷った地主の方にとって、一歩踏み出すきっかけになれば幸いです。


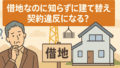
コメント