借地を引き継いだけれど、住めない…よくある状況と不安
親から家と土地を引き継いだ──それだけ聞くと、ありがたいことのように思えます。
しかし、その土地が「借地」だった場合、状況はまったく違ったものになります。
住む予定がない、建て替えもできない、地主とも付き合いがない…。
それでも固定資産税や地代は毎年請求され、気づけば「ただ持っているだけの不安な資産」に変わっていく──そんなケースが少なくありません。
遠方・別世帯・今の生活を変えられないという現実
借地付きの実家を相続しても、実際にそこに住める人は限られます。
すでに持ち家がある、遠方に住んでいる、家族の生活基盤が他にある——。
こうした事情から、「住む選択肢が現実的でない」という方はとても多いのです。
使っていないのにかかる費用(地代・税金・修繕)
家に誰も住んでいなくても、借地であれば地代の支払いは継続します。
また建物が残っていれば、固定資産税も課されます。
加えて、老朽化が進めば「草刈り」「雨漏り」「倒壊リスク」など、管理責任も発生。
「何もしていないのに出費だけが続く」というストレスを感じる人も少なくありません。
「いつか使うかも」と保留してしまいがちな心理
「子どもが独立したら住むかも?」「リモートで移住したら…」
そんな希望を捨てきれずに、判断を先延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。
けれど、その間にも土地の維持費はかかり、老朽化は進み、いざ住もうと思ったときには条件的に不可能ということも少なくありません。
次のステップでは、そんな「住めない借地」における、代表的な3つの選択肢とその判断軸について整理していきます。
住めない借地、3つの選択肢と判断軸
借地を相続したけれど、住めない。そんなときに検討できるのは、主に以下の3つの方向性です。
- ① 売る
- ② 貸す
- ③ 契約を解消する(家を解体し明け渡す)
それぞれにメリット・デメリットがあり、選択の判断軸も異なります。
【売る】借地でも売れる?地主との調整と価格の目安
借地権付き建物の売却は、一般の不動産よりも条件が複雑です。
地主の承諾が必要であること、第三者に譲渡しづらいことなどがハードルになります。
ただし、立地や建物状態によっては、借地権付きでも売却できるケースもあります。
売却益は低めになりがちですが、「維持するより手放したい」という判断には適している場合もあります。
【貸す】他人に貸せる?名義・契約・管理の落とし穴
「自分では住めないけれど、誰かに貸せれば…」と考える人もいますが、借地上の建物を賃貸に出すには地主の承諾が必要です。
また、契約や設備状況の整備がされていないと、トラブルになるリスクも。
地代・税金に加えて建物の維持管理責任も引き続き残る点には注意が必要です。
【契約解消】建物を解体し、借地契約を終了する選択
住む予定がない・貸すのも難しい・管理が負担——そんなとき、建物を解体して借地契約を終了するという選択肢があります。
地主の合意が必要ですが、「円満に土地を返す」ことで関係を保ったまま整理ができるケースも。
解体費用や原状回復の範囲など、実務面の確認は必要です。
判断のポイントは「費用・関係性・将来性」
こうして見ると、「売る」「貸す」「契約解消」のいずれも、地主との合意や調整が前提になることが分かります。
また、どれも「すぐに・簡単に」できる選択肢ではありません。
制度や契約の制限がある中で、自分の状況に合った“最適解”を選ぶことが大切です。
考慮すべきポイントは次の3つ:
- 維持・解体にかかる費用
- 地主との関係性(話しやすさ・承諾の有無)
- 今後その土地をどう使う可能性があるか(将来性)
次のステップでは、「契約解消」を選ぶ場合に必要な手続きや地主との調整について、実務的な流れを解説します。
手放すならどう動く?地主との相談・契約・解体までの流れ
住めない、貸せない、売れない…そんな状況で「もう手放したい」と思ったとき、どこから始めればよいのか分からないという声を多く聞きます。
ここでは、借地契約を解消するための基本的なステップを整理しておきます。
契約書で確認すべき項目(契約解消条項・原状回復)
まず確認すべきは借地契約書です。契約解消に関して、次のような項目をチェックしましょう:
- 契約の終了条件(期間満了/合意解除など)
- 建物解体や整地に関する原状回復義務
- 借地権の譲渡や転貸、解約における地主の承諾要件
契約書が古くて内容が不明瞭な場合は、専門家に見てもらうのもおすすめです。
家の解体費用と支払い負担の実務
建物を解体して更地にするには、一般的に50万〜150万円程度の費用がかかります(木造2階建ての場合)。
解体費用は借地人側(相続人)が負担することが多く、「明け渡す=解体して返す」というのが原則です。
また、建物が老朽化していると、安全性・近隣トラブル防止の観点からも早めの対応が求められることがあります。
地主との話し合いは誰と?どこに相談する?
地主と連絡が取れているなら、まずは「相談」というスタンスで事情を伝えましょう。
いきなり「解約したい」と切り出すより、「住む予定がない」「将来に不安がある」など背景を共有する方がスムーズです。
連絡先が分からない、うまく話せる自信がない場合は、司法書士や不動産相談窓口を頼るのも一つの手段です。
まとめ:迷っているならまず情報整理から
「手放したいけど、何をどう進めればいいか分からない」——それが一番多い悩みです。
まずは契約書・費用感・相談先の整理から始めましょう。
「とりあえず一度見てもらう」だけでも、進む方向が見えてきます。
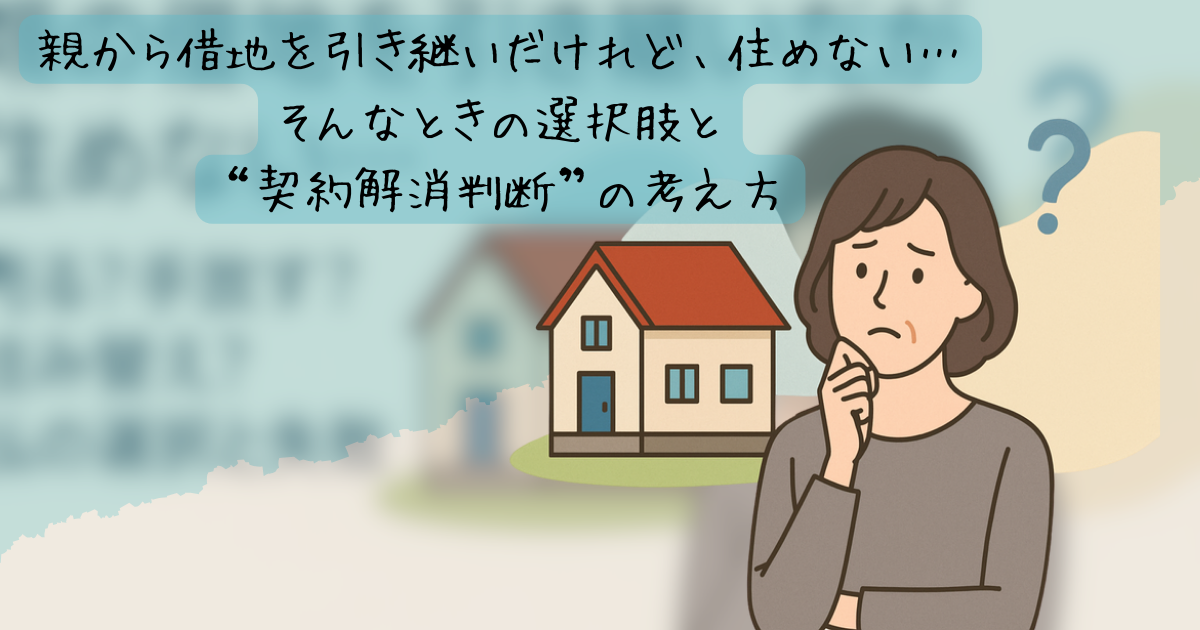
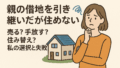

コメント