使用貸借と借地権って何が違うの?親族間で土地を貸すときに知っておきたい基本
「土地は親のものだけど、家は自分で建てたから大丈夫」
「うちは家族だから地代はもらってないよ」
そんな状態のまま年月が過ぎ、いざ相続や売却の局面になって、想定していなかったリスクやトラブルに直面するケースが少なくありません。
親族間で土地を貸すときに意識されることの少ない「使用貸借」と「借地権」。
この2つの違いは、法律上の扱いや税務、将来の権利主張に大きな差を生みます。
本記事では、その基本的な違いと実務上の注意点を、3ステップに分けてわかりやすく解説していきます。
使用貸借と借地権の違い|“ただで貸す”と“地代をもらう”は大違い
どちらも「他人に土地を貸す契約」だけど…
借地権とは、土地を建物所有目的で有償(地代あり)で貸す契約です。借地借家法が適用され、更新や立ち退きに強い保護が与えられます。
一方、使用貸借は無償で土地を貸す契約で、民法上の位置づけにとどまり、借地借家法の保護は受けられません。
両者の主な違いを簡単に整理すると:
| 項目 | 借地権 | 使用貸借 |
|---|---|---|
| 地代 | あり | なし |
| 契約の保護 | 借地借家法 | 民法 |
| 更新 | 自動更新あり | 明示しなければ終了可 |
| 登記の可否 | 登記で第三者に対抗可能 | 登記しても対抗できない |
使用貸借は契約があいまいでも成立する
親族間では「書面もないけど、使っていいって言われたから建てた」というケースが非常に多く、口約束でも成立するのが使用貸借の特徴です。
一方で、「地代をもらっていた」「契約書がある」という状態であれば、借地権とみなされる可能性が高くなり、法的保護も変わってきます。
「契約書がないとダメ」じゃなくて、「どんな契約だったか」が大事
「契約書がないから、うちは権利ないのかな…」
そんなふうに思ってしまう人も多いですが、実はちょっと違います。
たとえ書面がなくても、たとえば親の土地に長年家を建てて住んでいた、という関係があれば、
法律上“契約はあった”と判断されることもあるのです。
でも、そこで一番大事なのは、
「契約書があるかどうか」より「その関係がどんな契約だったのか?」という中身のほう。
たとえば…
- 地代を払っていた → 借地権の可能性が高い
- 地代なし、親の好意 → 使用貸借と見なされやすい
この“契約の性質”によって、法的な保護がまったく違います。
借地権なら、建て替えや譲渡、相続もできるし、土地の使用権として強い立場になります。
でも使用貸借なら、「返して」と言われたら返さないといけない、弱い立場です。
次は使用貸借のまま放置していると相続や所有者変更時にどんな問題が起きるか、具体的な事例で整理します。
使用貸借のままだと困るのはこんなとき|将来のリスク事例
親が亡くなったあと相続放棄されたら、“家を建てた人”が立場を失う?
使用貸借は土地を貸した人(親など)との信頼関係に基づく契約です。
そのため、土地の所有者が亡くなり、相続放棄などで第三者に所有権が移ると、使用貸借の効力が失われる危険があります。
たとえば:
- 親が亡くなり、他の相続人が土地を取得
- 家を建てて住んでいる人は「借りている」という書面もない
- 新たな土地所有者から「立ち退きを求められる」可能性がある
親族間の善意のやり取りが、法的には無効化されてしまうこともあるのです。
第三者に土地が渡ったとき、使用貸借では“対抗できない”
借地権であれば、登記がある場合は第三者に対抗できます。
つまり、所有者が変わっても、土地を使い続ける法的根拠になります。
一方、使用貸借では:
- 登記しても第三者への対抗力がない
- 使用している事実だけでは保護されにくい
相手が親族ではなくなった途端に、「不法占拠」とみなされるリスクさえあるのです。
使用貸借のつもりが贈与税を問われるケースも
使親族間で「ただで使っていいよ」と言われて家を建てたり、
契約はあいまいだけど長年その土地を使わせてもらっていたり――
そんなケースって、実際とても多いと思います。
でも実は、こうした状況、「使用貸借」としてのリスクだけでなく、
場合によっては「贈与」と見なされてしまうこともあるんです。
たとえば…
- 地代を払わずに長年そのまま使っている
- 建てた家を人に貸して利益を得ている
- 契約書がなく、土地の使い方や立場があいまいなまま
という場合、税務署から
「それって実質、借地権を無償でもらった状態ですよね?」
と判断されてしまうことがあります。
つまり、本当はそんなつもりじゃなくても、
「価値のある権利をもらった=贈与」とされてしまうことがあるんです。
次はこうしたリスクを避けるために、親族間で土地を貸すときに整えておきたい契約や書類についてご紹介します。
親族間で土地を貸すときの“守り方”|契約と記録のすすめ
相手が家族でも契約書を作成しておくメリット
「親子間だから大丈夫」「兄弟だから信頼している」
そう思っていても、世代交代・相続・売却の場面では第三者が出てきます。
家族間のやり取りを法的に守るには、使用貸借契約書を残すことが大切です。
契約内容の例:
- 貸与目的(土地上に建物を建てる)
- 地代を徴収しないこと
- 返還期限・終了条件の明記
借地契約とする場合は、地代を設定し、借地権としての登記まで行えば、第三者に対する“対抗力”が強化されます。
登記・公正証書など“後で証明できる形”を残す
契約書のほか、以下のような記録もおすすめです:
- 契約書の公正証書化
- 建物の登記(誰の所有か)
- 貸主・借主の双方で署名・押印した覚書
「いつ、誰と、どんな約束をしたか」を示せる記録があれば、将来的なトラブル回避につながります。
「土地に少し名義を持たせる」はどうなの?
たとえば、建物所有者に土地の持分を1%だけ与えるという方法も検討されることがありますが、実務上は慎重に判断すべきです。
理由としては:
- 共有状態になると、将来の相続・売却が面倒
- 税務署に“形式的な贈与”と見なされる可能性
- 名義だけでは「使用権」の根拠になりにくい
目的が「住み続ける安心感」なら、きちんと契約や登記で整備するほうが確実です。
まとめ:「家族だから大丈夫」では守れない時代へ
親族間の善意や信頼は大切なものですが、契約や登記がなければ、第三者には通用しないのが現実です。
「今は問題ない」からこそ、今のうちに契約書や記録を残しておくことが、将来の安心につながります。
後になって「こんなはずじゃなかった」とならないように、今の状態を法的に整理しておくことを、ぜひ検討してみてください。
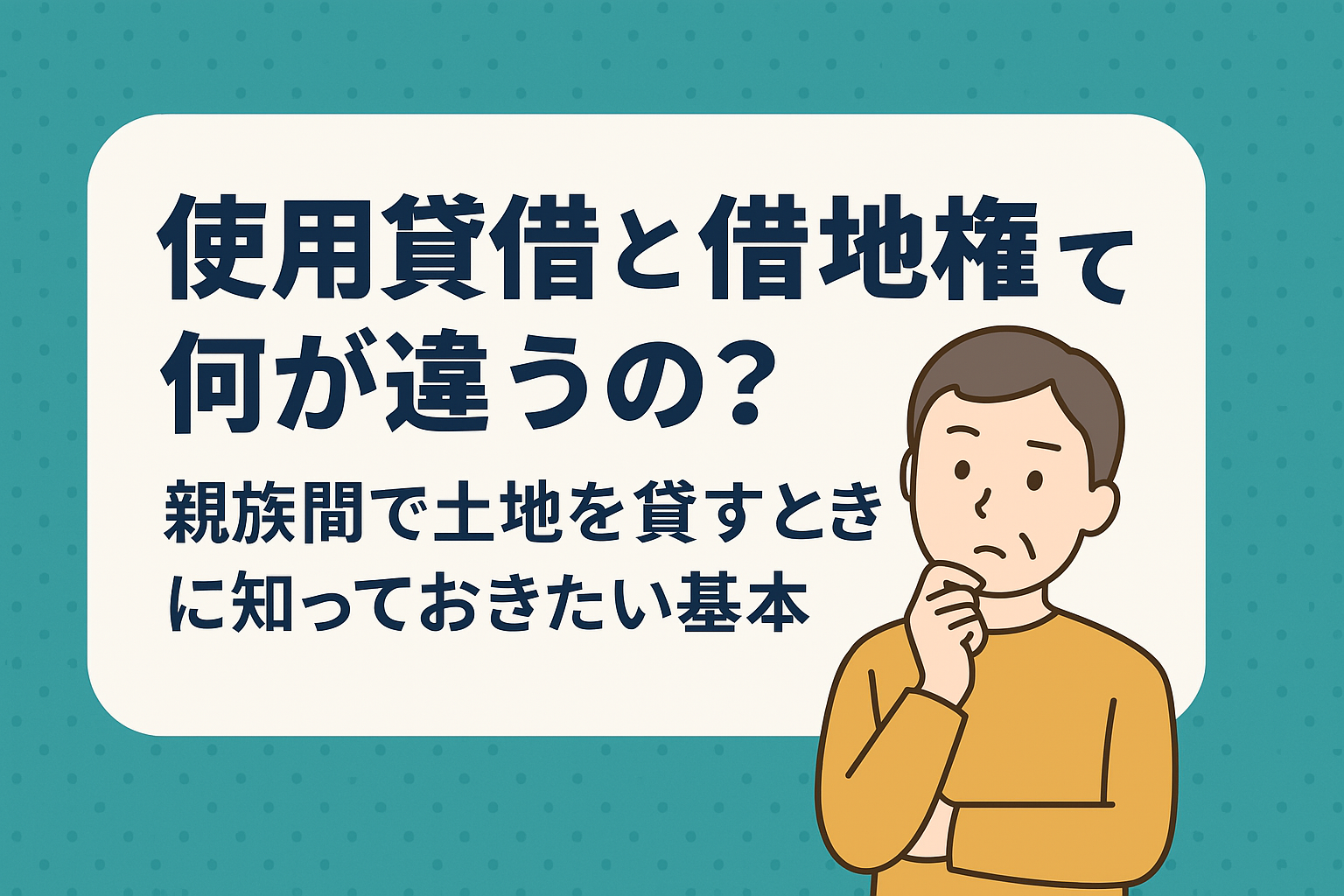
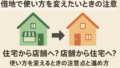
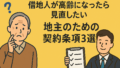
コメント