Aさんのケース──「親の土地」と思って建て替えたら…
Aさんの場合:親の代では信頼で成り立っていた借地だった
Aさんの実家は、父親が長年住んでいた借地の上に建てられた一戸建て。
借地といっても、地主との関係は良好で、地元の顔見知り同士。家の名義は父、土地は地主という形でしたが、「ほとんど持ち家のようなもの」と感じていたといいます。
実際、父と地主は30年来の付き合いで、更新や地代の話も「世間話の延長」で済んでいたほど。
そんな実家を相続し、住み続けることになったのが、息子であるAさんでした。
古くなった家を建て替えようと思ったとき、Aさんは「もちろん問題ない」と思い込んでいました。
長年仲の良かった地主と親。形式的な借地だったけれど…
Aさんにとって、実家は「土地と家は別の所有だけど、特に気にしたことがなかった」場所。
契約も更新されており、父が他界したときに新たな契約書が取り交わされていましたが、「親の代と変わらないだろう」と特に確認していなかったのです。
建物が古くなり、息子夫婦が建て替えを決意
築40年を超えていた実家は老朽化が進んでおり、耐震性にも不安がありました。
「このままでは家族が安心して住めない」と、Aさんは建て替えを決意。すでに業者にも相談し、工事の段取りまで組んでいたといいます。
工事開始直前に地主から「契約違反では?」の一言
地鎮祭を終え、工事が始まろうとしていたタイミングで、久しぶりに顔を出した地主から、
「建て替えって…うちに話、あったっけ?」という一言。
驚いたAさんが確認すると、契約書には「建て替え時は事前の承諾が必要」との文言がしっかり記載されていたのです。
「えっ…契約書、そんな風に読んでなかった」「親父のときはそんなのなかった」──
思い込みと確認不足が、トラブルの火種となっていたことに、このとき初めて気づきました。
なぜこうなった?引き継ぎ世代で起きた“認識のズレ”
Aさんにとって、地主は親の友人のような存在であり、「何かあっても話せばわかってくれる」と思っていました。
でも、現実には親の代で成立していた“信頼ベースの関係”と、Aさんの契約関係は別物だったのです。
契約書には「建て替え時は承諾が必要」と明記されていた
実際に取り交わされた契約書には、「建物を建て替える場合、地主の事前承諾を得ること」と明記されていました。
しかしAさんは、「更新のときに簡単な説明を受けただけ」「細かい内容までは読まなかった」といい、事実上、契約の重要部分を認識していなかった状態でした。
親からは「大丈夫よ」と聞かされていたが…
契約引き継ぎの際、Aさんは「うちは昔からの関係だから心配ないよ」と親から言われていたそうです。
しかし、親の代の“信頼”と、子世代の“契約の義務”は別物でした。
「昔の関係性」と「今の契約」のギャップに気づかなかった
地主としては、「代替わりしたからこそ、契約に沿って対応してほしい」という意識が強く、
「一言も相談がなかった」と感じたことで、関係にヒビが入りかねない状況になってしまいました。
次のステップでは、建て替えを巡るトラブルの実際と、Aさんと地主がどう向き合っていったのかを紹介します。
契約違反になるとどうなる?地主との話し合いの行方
「契約違反では?」と言われたとき、Aさんは何がいけなかったのかもわからない状態でした。
「これまでうまくやっていたのに、なぜ急に…」という気持ちと、「話し合えばなんとかなるだろう」という淡い期待が交錯していました。
建て替え中断→合意形成までの交渉の流れ
工事業者にも一旦ストップをかけ、Aさんは地主に謝罪と説明の場を設けました。
地主からは「言ってくれればよかった」「無断で進められるのが一番困る」という言葉があり、建て替え自体は否定されませんでしたが、“手順を踏まなかった”ことが大きな問題となっていたのです。
「勝手に進められた」と不信感を持たれた理由
地主としては、「代替わりしたからこそ、きちんと話をしてほしかった」という思いがありました。
一方でAさんは「まさかこんなことで…」という思いが強く、認識のズレと感情の行き違いがトラブルの本質でした。
承諾料や契約内容の見直しを求められた現実
最終的に、建て替えについては正式な書面での承諾を交わすことで合意に。
地主側からは承諾料として数十万円を求められ、また今後の契約内容についても「更新料・連絡義務」など細かな点を見直すことになりました。
「昔はそんなのいらなかった」という気持ちは残りつつも、Aさんは“関係を続けたいなら今のルールに従うしかない”と実感したそうです。
次のステップでは、同じようなトラブルを避けるための具体的な対応策を紹介します。
トラブルを避けるには?代替案と防ぐべきポイント
今回のようなトラブルは、「建て替えそのもの」ではなく、手続きや確認が不足していたことが原因でした。
承諾書・工事通知など書面で残す重要性
たとえ口頭で話していたとしても、「聞いてない」「そんなつもりじゃなかった」というすれ違いは簡単に起きます。
工事の前に「建て替えの予定があります」と書面で通知したり、承諾書をもらっておくだけで、こうした誤解の多くは防げます。
「親の代では問題なかった」は通用しない
親の時代は良好な関係で成り立っていたとしても、世代が変われば契約は契約。
「うちは昔からだから」は、残念ながら多くの場合通用しません。
相談や調整は“先に”“必ず”やるべきだった
トラブルを避けるためには、「あとで報告」ではなく“先に相談”が基本です。
たとえ「言わなくても大丈夫だろう」と思っていても、報告・相談・合意形成は信頼関係の要。
特に契約に基づく関係では、それが最低限のルールになります。
まとめ──引き継いだ借地、次世代こそ慎重な確認を
「昔は問題なかったのに」「親のときはもっと気楽だったのに」──
そう思うことは自然ですが、世代交代のタイミングは、契約を見直すタイミングでもあります。
関係を壊したくないと思うならこそ、事前の確認・相談が誠実な対応になります。
この記事で得られたかもしれない“気づき”
- 建て替えには地主の承諾が必要なことが多い
- 契約書に書かれていても、見落とされがち
- 親と地主の関係と、自分の契約は“別もの”
借地を引き継いだときは、「契約を一度しっかり確認する」ことが、次のトラブルを防ぐ第一歩です。
「これ、うちも似てるかも…」と思った方は、今からでも遅くありません。
ぜひ一度、契約書を開いて、家族と一緒に見直してみてください。

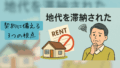
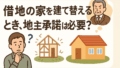
コメント