Kさんのケース──親の借地を引き継いだが、住めなかった
Kさんの場合:実家をどうするか、想像よりずっと難しい選択だった
50代のKさんは、地方にある実家の借地を相続することになりました。
親の死後、家はそのまま残り、名義は自分へ。形式的には「引き継いだ」ことになります。
しかしKさん自身は、東京郊外に夫と子供と暮らしており、子供はまだ学生。
自宅から実家までは新幹線を使っても片道4時間。生活の拠点を移すのは非現実的でした。
「いつかリモート勤務になったら…」そんな淡い期待を抱きながらも、日々の忙しさの中で判断を先送りにしていたKさん。
けれど1年、2年と経ち、草が伸びた庭や、地代通知、固定資産税の請求書が届くたびに、
「私、この家をどうするつもりなんだろう?」という不安が少しずつ重くのしかかっていきました。
親が亡くなり、突然やってきた「借地付き家」の問題
Kさんにとって、親の死はもちろん大きな出来事でしたが、それ以上に現実を突きつけられたのが「相続後に残された家」の存在でした。
名義変更や書類の手続きは、司法書士に頼んでスムーズに済みました。
でも、その後の「この家をどうするか」は、誰も教えてくれないテーマでした。
「戻る」という選択肢は、現実的ではなかった
「実家を継ぐ=そこに住む」という選択肢も、一瞬は頭に浮かびました。
でも、子どもの学校、夫の仕事、そして自分自身の今の生活——あまりにも現実とかけ離れていたのです。
「家だけならまだしも、借地って…?」と初めて契約書を開き、地代の支払い、更新の時期、建て替え不可の条項を見て、一気にプレッシャーを感じたと言います。
「とりあえず置いておこう」が招いた、想像以上の重さ
「すぐに決めなくてもいいよね」「どうせ急いでも住めないし」——Kさんは、そう言い聞かせながら、手をつけずに時間だけが過ぎていきました。
でも、庭の草は伸び続け、地代の請求は届き、税金は自動で引き落とされていく。
使ってもいない家に、毎月お金と心配だけが積み重なっていく日々。
「あのとき、誰かに相談していれば…」
Kさんの経験は、今、同じように悩んでいる誰かにとっての“先に知っておけること”かもしれません。
同じように「動けずに困っている人」は意外と多い
実家を相続したものの、借地という制約の中で「どう動けばいいか分からない」という人は、決して少なくありません。
とくに遠方に住んでいたり、子育て・介護・仕事などを抱えていると、判断が後回しになるのは当然です。
相続しても、すぐには住めない・売れないのが借地のリアル
一般の不動産とは違い、借地には建て替えや転用に制限があり、「自由に処分できるものではない」というのが現実です。
さらに売却には地主の承諾が必要なケースも多く、住めない・貸せない・売れないという三重苦に悩む人も。
契約内容がハードルになることも
「住める家があるのになぜ使えないのか?」──Kさんもそう思いました。
しかし借地契約の中には、「建て替えには承諾が必要」「契約更新の時期が近い」「地代の改定が予定されている」など、住み始める前からハードルが高いケースが多いのです。
“判断を先延ばしにしている人”ほど、不安を抱えやすい
現実的にすぐ住めない。売れる見込みも立たない。
「じゃあどうすればいいの?」という悩みは、動けないまま放置され、精神的な負担として積み重なっていきます。
Kさんのように、迷ったまま何年も過ぎてしまう人も少なくありません。
なぜうまくいかなかったのか?選択を誤りやすい3つの分かれ道
Kさんの選択は決して間違いではありませんでした。
でも「もう少し情報があれば」「誰かに相談できていれば」、もっと違う未来もあったかもしれません。
1. 「そのままにしておけばいい」という甘さ
家はそのまま。契約はとりあえず維持。
でも借地には地代・契約更新・維持管理の責任がつきまといます。
何もしなければリスクは増えるだけ。これは、住んでいない土地でも同じです。
2. 地主との関係を築けていなかった
地主との連絡は「親の代で終わっている」ケースが多く、新たな借地人(相続人)として、改めて関係を築く努力が必要です。
Kさんも「顔も知らない地主に突然売却の話は切り出せなかった」と言っていました。
3. 情報が足りないまま判断していた
借地に関する制度や選択肢を知らないまま、「なんとなくの判断」で行動してしまうと、後で後悔することも。
住めない、売れない、貸せない──でも本当にそうか?
選択肢を知ることが、後悔を減らす第一歩になるのです。
次のステップでは、Kさんのような状況から「今できる見直しと判断の軸」を具体的に整理していきます。
今からでもやっておくべき“見直し”と選択肢の整理
Kさんは、最終的に「解消」を選びました。
地主と連絡を取り、借地契約を終了。家を解体し、更地に戻して明け渡すことで、ようやく心の負担から解放されたといいます。
もちろん費用も手間もかかりましたが、「このまま何年も悩み続けるより、区切りをつけられてよかった」と語ってくれました。
借地を相続したら、まず「契約と状況の確認」から
・契約内容はどうなっているか?
・更新時期や地代の有無は?
・建て替えや転用の制限は?
最初にこれらを確認するだけで、動ける選択肢の幅が大きく変わります。
住む?売る?手放す?まずは家族と優先順位を明確に
すぐに決める必要はありません。でも「何も考えないまま保留」だと、Kさんのように何年も不安を抱え続けることになります。
「誰が管理するのか」「どこまで手をかけられるのか」などを、家族と話し合っておくことも重要です。
使う予定がない借地は“整理フロー”を知っておくと安心
- 契約書・登記の確認
- 地主との相談・合意形成
- 家の売却または解体、土地の明け渡し
不安を抱えたままにするより、「使う予定がないなら手放す」という選択肢も、前向きな行動と言えるのではないでしょうか。
まとめ──Kさんが最後に伝えたかった「同じ悩みを抱える人へ」
「どうするか分からないから、何もできなかった」
Kさんは、そう語っていました。
でも今では、「早く誰かに相談すればよかった」と思えるようになったそうです。
この記事を読んで、もし「うちも似てるかも」と感じた方がいれば、それは動き出せるサインかもしれません。
借地という言葉にとまどう気持ち、遠方にあって後回しにしてしまう現実、家族との温度差。どれもKさんが通ってきた道です。
だからこそ、悩みを抱えたまま動けないあなたへ、「まずは相談してみてください」と、Kさんは伝えたいのです。
▶ 借地を引き継いだものの活用に悩んでいる方へ、こちらもどうぞ:
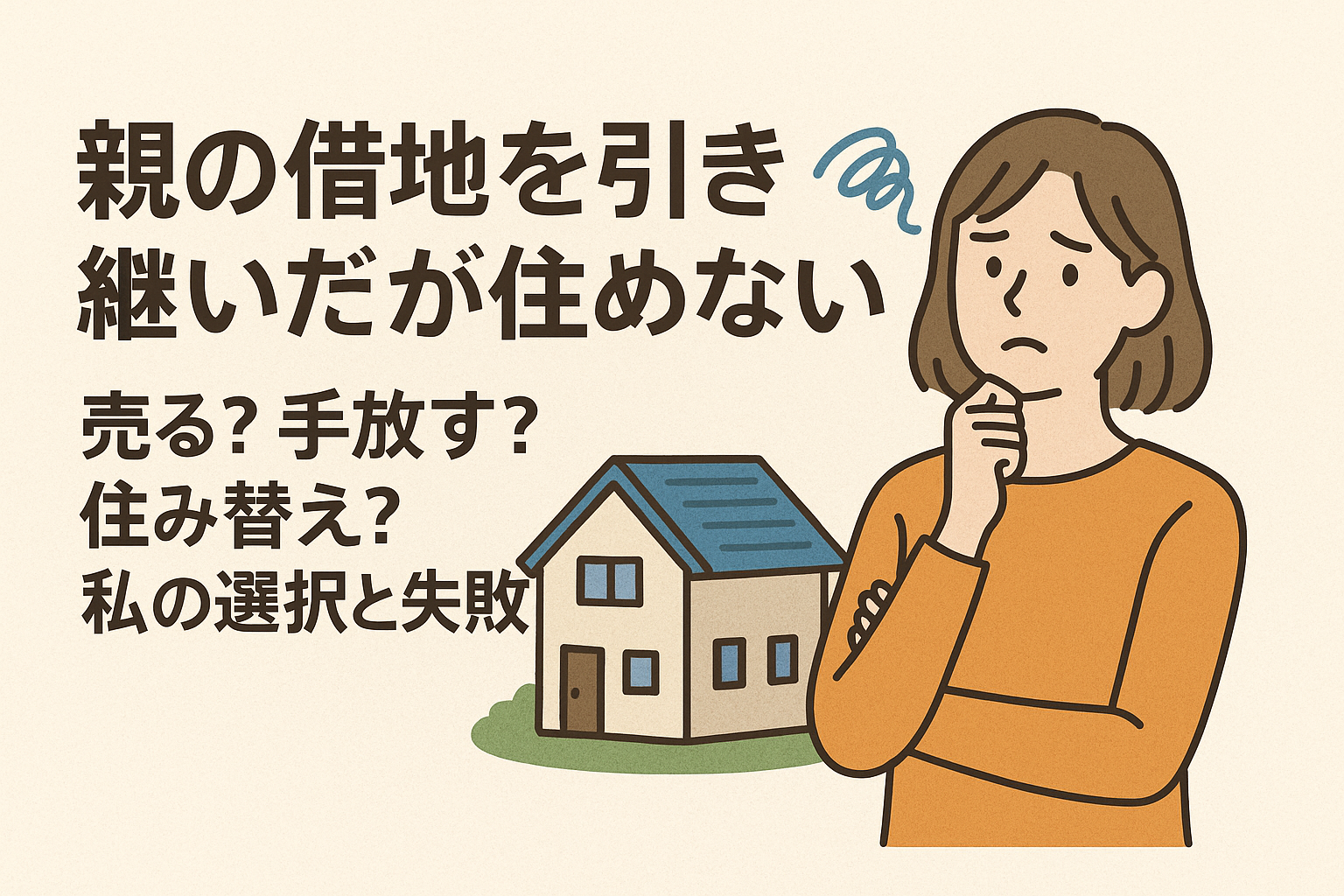
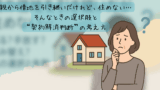


コメント