Aさんのケース──借地人がいなくなり、家だけが残された
Aさんの場合:気づけば、誰もいない家が残されていた
父から引き継いだ借地付き土地を管理していたAさん。借地人とは長年のつきあいがあり、地代の入金も滞りなく続いていました。
しかしある年、地代が遅れがちになり、数か月後には入金が途絶えました。気になって現地を訪ねると、ポストにはチラシが溜まり、庭は雑草で覆われていました。近所の方に尋ねると「半年くらい誰も見てないと思う」とのこと。
その後の調査で、借地人はすでに亡くなっていたことが判明。さらに相続人は相続放棄しており、建物も土地も、誰も手をつけないまま放置された状態でした。
Aさんは困惑しました。契約は続いているのか?家は壊せるのか?固定資産税はかかり続ける中、相談先も分からず、長い時間だけが過ぎていきました。
「最近、地代が入ってないな」から始まった違和感
地代の未払いにすぐ気づいたAさんでしたが、「一時的なものかもしれない」「事情があるのだろう」と様子を見る形に。
こうした対応はよくあるもので、すぐに法的対応に移るのは心理的にも難しいものです。
借地人は死亡、相続人はいない…突然の“無人化”
市役所経由で調べた結果、借地人が既に亡くなっていたことがわかりました。
さらに戸籍を追っていくと、複数の相続人がいたものの、全員が相続放棄済み。結果、契約の相手方が存在しない状態となりました。
これは想定しづらい事態ですが、実際に起きています。
家が残っても壊せない。困惑と不安の毎日
誰も住まない家が、誰の手にも渡らずに残る。
Aさんは「勝手に壊すわけにもいかない」「でも、放置していては不法侵入や倒壊のリスクもある」と、板挟みの状態に。
しかも、建物が残っている限り土地の評価は下がらず、固定資産税の負担は続く。
Aさんは、「ただ待つしかないのか」と、孤独な時間の中で答えを探していました。
同じようなケース、実はあちこちで起きている
「うちは特別なんじゃないか」「こんなケース、他にもあるの?」──
Aさんのような悩みを抱える地主の声は、実は全国の相談窓口に数多く寄せられています。
地代が止まり、家が放置される…増えている“無人借地”の実態
近年、地代の未払いをきっかけに借地人の不在が発覚するケースが増えています。
借地人が高齢で孤立していたり、親族との関係が希薄だったりする場合、死亡後に誰にも引き継がれないまま放置されてしまうこともあります。
中には、「借地権を放棄したつもりでそのまま出て行ってしまう」ケースもあり、法的には放棄されていなくても、事実上“消えてしまった借地人”となる例があるのです。
契約者不在のまま…地代も請求できず、土地も使えない
借地契約は「地代を払ってもらう代わりに土地を貸す」という関係ですが、借地人が不在だとそのバランスが崩れます。
相続人が現れれば契約交渉もできますが、相続放棄があると誰に請求すればいいのか分からない状態に。
しかも、家が残っているせいで他の活用もできず、売却も不可という“八方ふさがり”に陥るのです。
制度があっても「知っている人が少ない」という現実
実は、こうしたケースに対応するための制度(例:相続財産管理人制度)はあります。
しかし、地主側が存在を知らなかったり、動くタイミングを逃したりしてしまうと、何年も放置されたままになることも少なくありません。
これは「制度が足りない」のではなく、制度にアクセスできるかどうかの問題です。
次のステップでは、Aさんのケースから見えてきた、なぜこうなってしまったのかを振り返り、見落とされがちな課題を整理していきます。
なぜこうなったのか?見落とされがちな“3つの課題”
Aさんのケースを振り返ると、「もっと早く対応できたのでは」「こうしておけば避けられたかも」と感じるポイントがいくつかあります。
ここでは、同じような事態を防ぐために見直すべき3つの課題を整理してみましょう。
1. 契約条項に「使用義務」や「緊急連絡先」がなかった
借地契約には、住居としての使用義務や、契約者の不在時の連絡先を定める条項が盛り込まれていないケースも多く見られます。
こうした条項がないと、借地人の不在や死亡があっても地主がすぐに把握・対応する手段がなく、結果的に放置されやすくなってしまうのです。
2. 高齢借地人とのコミュニケーションが希薄だった
借地人が高齢になるにつれて、地代の入金や書類のやりとりが曖昧になることがあります。
しかし、「長年の付き合いだし…」と遠慮していると、気づいたときにはすでに相続放棄後という事態にもなりかねません。
定期的な声かけや、家族・後見人とつながっておくことで、早めの気づきと対応ができたかもしれません。
3. 地代の遅れを「まあいいか」で済ませていた
最初のサインは「地代の入金が遅れた」ことでした。
しかしAさんは、「事情があるのだろう」と様子を見ることを選びました。
結果として対応が後手になり、法的な整理にも時間と費用がかかる状態に。
小さな異変に気づいたときに、声をかけたり通知を出したりすることが、将来のリスクを減らす第一歩になるのです。
では、もし同じ状況になったとき、地主はどう動けばよかったのでしょうか?
次のステップでは、制度や手続き面で「できたはずの対応」を整理していきます。
本当はどう動けたのか?知っておくべき制度と手順
「もっと早く動けていれば…」──Aさんのような後悔をしないために、地主が知っておきたい手続きと制度を紹介します。
知らなければ動けない。でも、知っていれば備えられることも、たくさんあるのです。
内容証明で“催告”することの意味
借地人と連絡がつかないとき、まずとれる行動が内容証明郵便での催告です。
「何月分の地代が未納」「いつまでに支払いがなければ解除を検討」といった事実を明記して送付することで、後の契約解除や法的整理の準備になります。
宛先は登記上の住所でOK。返送された場合でも記録として有効なので、迷わず動いておくことが大切です。
「相続財産管理人」という選択肢がある
相続放棄により契約相手がいない場合、地主が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。
選ばれた管理人は、残された財産(=建物など)の整理・処分を行い、地主との契約関係の清算や明渡しの手続きも進めてくれます。
申立てには数万円〜十数万円の予納金がかかることもありますが、「動けない状態」から抜け出す唯一の道になる場合もあります。
家の撤去や明渡しも「勝手に」はできない
家が残っていても、登記が借地人名義のままである限り、地主が勝手に壊すことはできません。
だからこそ、「管理人を通して法的に処理する」「撤去・明渡しの手続きを正式に行う」ことで、トラブルなく土地を取り戻すことが可能になります。
次のステップでは、こうしたトラブルを繰り返さないために、地主として今からできる備えについて考えていきます。
まとめ──“同じことを繰り返さないために”できる備えとは
Aさんが直面したのは、誰にでも起こりうる現実でした。
借地人がいなくなり、契約はそのまま、家は壊せず、地代は入らない──放っておけば状況は悪化するばかりです。
でも、もし次のような備えがあれば、結果は違っていたかもしれません。
- 契約更新時に「使用義務」や「緊急連絡先」を盛り込む
- 借地人の高齢化に合わせ、家族や後見人とつながっておく
- 小さな違和感(未納・連絡不能)を放置せず、早めに催告する
これらは“トラブルを防ぐ仕組み”であると同時に、地主自身の安心を守る手段でもあります。
そしてもし、すでにAさんのような状況が始まっているなら──
今こそ、専門家や制度に頼る第一歩を踏み出すタイミングです。
放置すれば負担が増える一方。でも、行動すれば“整理の道”は見えてきます。
「うちも似てるかも…」と感じた方は、ぜひ無料相談なども活用してみてください。
▶ 同じようなケースでお困りなら、こちらの記事も参考になります:

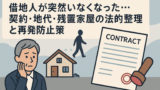
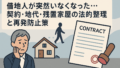
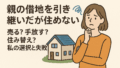
コメント